こんにちは。フォルテの理系担当佐々木です。
今日は勉強においてとても需要な『集中力を高める方法』について書きたいと思います。勉強しようと思っていてもなかなか集中力が続かずにダラダラしてしまって、結局時間だけが経っていったなんて言う人も多いのではないでしょうか?では、どうすれば集中力が続くのか?意志や忍耐力が足りないから集中力がないのか?何か特別な方法はないのか?などについて書いていきます。
集中力が続かないのは意志が弱いからではない。
集中力が続かないのは、意志が弱いからとかやる気がないからとか忍耐力がないからではありません。例えば、好きなゲームをしていたり漫画を見たりしていると、1時間や2時間があっという間に経ってしまった!なんていうことがある人は、集中するのに必要な最低限の力は持っているということになります。集中力を引き出すやり方さえ知っていれば、意志の強さは必要ありません。中には、『本気になれば集中できる』などと考えている人もいますが、その『本気』がくる数日後にテストや入試が来たのでは時すでに遅しです。また、自分の本気に過度の期待を抱いていても、思ったほど集中出来ていない自分にショックを受けてしまうことになるでしょう。では、どうすればよいのでしょう?集中できないのは自分が悪いのではなく、集中するためのテクニックを知らないからです。
困難は分割せよ。
よく人間の集中力は最大で90分だとか言われていますが、特に科学的根拠はありません。正直、90分間も集中していられるという人はとても少ないと思います。むしろ60分でも長いと思います。そう考えると、適度に分けていく方が賢明です。そこで、この名言の登場です。
「困難は分割せよ。」
これは近代哲学の祖と言われているデカルトが『方法序説』の中で述べた言葉です。また、中3であれば、国語の教科書に載っている井上ひさしの『握手』でルロイ修道士が言っていたセリフとしても思い浮かびますね。「どんなに難しいことでも細かく分けていけばやり遂げることが出来る」というような意味で、まさに勉強においてもピッタリ当てはまるのではないかと思います。取り組むべき内容を細かく分けることで覚えやすくなったり、集中力が続いたりします。
例えば、ケータイ電話の番号を単純に090□□□□△△△△とするのではなく、090-□□□□―△△△△のように分けた方が覚えやすかったりします。また、一般的なテレビドラマは1話が約1時間(CM含むので実際は40分ちょっと)のものが多いですが、1話を圧倒的に短くしてもしっかりと成立している例として、NHKの連続テレビ小説、通称『朝ドラ』があります。毎朝15分(日曜日を除く)という短さにも関わらず、常に高視聴率を取り続けています(私はあまり見ていないですが・・・)。これが毎朝、40分ほどの長さだと、流石に朝からそこまで集中してみる人は少なくなるでしょう。
もっと短い例としては、今年で放送50周年を迎える、世界で最も長く放映されているテレビアニメ番組としてギネス世界記録を更新中の『サザエさん』があります(私が子供の頃は、日曜夜の定番として、6時からの『ちびまる子ちゃん』を見て、6時半からの『サザエさん』を見るというのがゴールデンパターンでした)。『サザエさん』は30分(CM含むので実際は22分ほど)の番組で、1回の放送が3話構成になっているため、1話がなんと6分55秒という衝撃の短さです。7分足らずで1つの物語を完結させているなんて凄すぎますね。この構成も『サザエさん』が長年愛される秘密なのかもしませんね。
これらの例のように、物事を細かく分けることは様々な場面で有効なのです。これは余談ですが、『サザエさん』はなぜ海にちなんだ名前が多いのかご存じでしょうか?原作者の長谷川町子さんが、仕事を依頼されてから、どんな内容にするかを妹さんと一緒に毎日海岸を散歩しながら考えていたので、登場人物がみんな海産物の名前になったらしいです。
「ポモドーロテクニック」とは
それではここで主題である「ポモドーロテクニック」について紹介していきます。「ポモドーロテクニック」とは1990年代前半に、イタリアの起業家であり作家でもあるフランチェスコ・シリロ氏によって生み出された、仕事や勉強の成果を高めるための方法です。
やり方を簡単に説明すると、
① やるべきタスク(課題)を選ぶ。
② キッチンタイマーで25分を設定する
③ キッチンタイマーが鳴るまでタスクに集中する。
④ 3~5分間休憩する。
⑤ ①~④までの作業を「1ポモドーロ」として、これを4ポモドーロ行う。
⑥ 4ポモドーロ終えたら15分~30分休憩する。
これを繰り返していくだけです。この「25分集中」+「5分休憩」を繰り返し、4回繰り返したら長めの休憩を入れるという時間管理術が「ポモドーロテクニック」です。高い集中力を長時間保ち続け、生産性を向上させるのに役立つ方法として知られています。
「ポモドーロテクニック」の優れている点は、25分間という短い時間で休憩をはさむため、ストレスがほとんどたまらずに取り組めることです。それにより、勉強がはかどり、集中が続き、気づいたら時間が過ぎていきます。疲れたと思い始めたころには長めの休憩が入るため、長時間勉強していてもそれほど苦になりません。
ただし、どんな良い方法でも実際にやらなければ効果はありません。「今はまだ勉強をやる気が起きない。テストが近くなってきたらそのうちやる気が出るだろう。」と思っている人がいるかもしれませんが、やる気は待っていても起きません。テストの数日前に慌てふためいても後の祭りです。まずは、行動してみましょう。やってみると意外と25分が短く感じればしめたものです。行動することにより、やる気が出てきます。
ちなみに「ポモドーロ」とはイタリア語でトマトの事で、フランチェスコ・シリロ氏が学生時代に使っていたトマト型のキッチンタイマーにちなんでつけられたそうです。私がこの「ポモドーロテクニック」を知ったきっかけは、メンタリストDaiGo氏の著書『自分を操る超集中力』で紹介されていたからです。この本は集中力を上げるための具体的な方法がたくさん載っているので気になる方は是非読んでみてください。
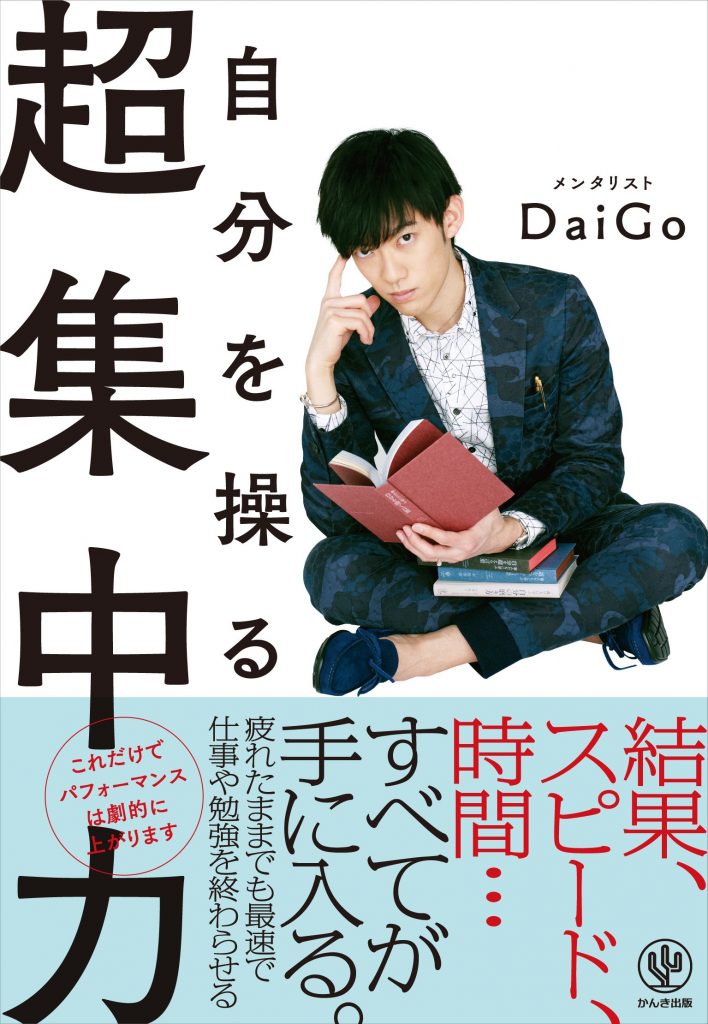
集中力を高める方法「ポモドーロテクニック」
「ポモドーロテクニック」において必要な道具はキッチンタイマーのみです。このキッチンタイマーについてはなるべく1分や1秒ずつではなく、ワンタッチで10分計ることが出来るものなどを活用しましょう。
例えば、フォルテにあるのがこちらです。

ケータイのアプリ等で計ってもよいのですが、目の前にケータイを置いておくと、ついいじってしまったり、ラインが来たりして気が散ると良くないので、自制心のがよほど強くない限りは、なるべくキッチンタイマーを活用しましょう。それと、「25分集中」の時にケータイがなったりすると勉強の妨げになるので、ケータイもサイレントモードや思い切って電源を切るなどして集中できる環境を作りましょう。
そして、最も重要なことがポモドーロの途中で中断しないようにすることです。中断には内的要因と外的要因の2種類が考えられます。内的要因は、のどが渇いたり、急に誰かに連絡する用事を思い出したり、メールやラインをチェックしたくなったりすることです。
このような形で作業が止まってしまったり、先延ばししたりする内的中断が起こらないようにするには、事前に水分補給をしたり、緊急の用事以外は連絡を取るのは長い休憩時間の時のみにすると決めておくことです。
一方で外的要因は、一人ではなく複数で勉強している場合などに起こることが多くなります。例えば、一緒に勉強している友達からわからない所を質問されたり、勉強している最中にご飯食べに行こうなどと誘われたりする外的中断に対しても、あらかじめルールを決めておくと良いと思います。わからない所や伝えたいことがあったら、休憩時間の時に聞いたりして、極力ポモドーロを守ることを最優先にしていきましょう。
また、「ポモドーロテクニック」において、休憩の使い方も非常に重要です。「25分集中」した後の「5分休憩」もしっかりキッチンタイマーで計りましょう。「気が付いたら10分も経っていた」などとならないようにするのと、「よしっ。タイマーがなったからまた25分間頑張るぞ」という、次のポモドーロにスムーズに移行するためです。また、「5分休憩」の時にケータイでメールやラインの返信を行ったりすると、再度返信が来たりして気になってしまい集中を乱すもとになりかねないので、出来る限りケータイをいじるのは4ポモドーロ終了時の長い休憩の時のみにしましょう。「5分休憩」では、体操をする・歩く・筋トレするなど体を動かしたり、水分を補給したり、瞑想したりするのがお勧めです。そもそも「5分休憩」するのは何のためかを考えると良いでしょう。ゆったりくつろぐのではなく、勉強の生産性を上げ、集中力を持続させるのが目的です。
また、1ポモドーロの「25分間」では、基本的には1つのことに集中しましょう。例えば、数学の問題を解いていたと思ったら英単語を覚え始めたり…とならないように。数分で終わるものが幾つかあって、それを組み合わせて1ポモドーロにせざるを得ないときはしょうがないですが、理想は、「このポモドーロでは数学の方程式の問題を解くぞ」となれば、それ以外の余計なことを考えなくて良いので、「方程式の問題を解くこと」に全ての力を注ぐことができ、集中力が高まります。
苦手科目の克服にも役立つ「ポモドーロテクニック」
苦手科目がないという人はあまりいません。では、その苦手科目を克服するにはどうすれば良いのでしょうか?苦手科目というのは、そもそもその科目にかける勉強時間が少ないから苦手なわけです。「一番熱心に時間も労力も注いでいるけれど、苦手です。」という人はまずいませんよね。やらないから、出来ない。出来ないから楽しくない。そうするとますますやらなくなり、そのままにしておくとやがて取り返しがつかなくなります。
本来勉強は、最初のうちは苦手だとしても、理解して出来るようになるとそれなりに面白く感じるようになります。ですので、まずはその科目に費やす勉強時間を増やすようにしましょう。いきなり苦手科目を1時間勉強するのは大変だと思うので、例えば、『このポモドーロでは苦手の英語を勉強して、次のポモドーロでは得意の数学をやろう』というように、まずは25分間苦手科目の克服に時間を割きましょう。それが出来るようになってきたら、2ポモドーロ(50分間)にチャレンジしてみましょう。2ポモドーロ連続でやるのが難しければ、例えば「英語を25分間集中」⇒「休憩5分」⇒「数学25分間集中」⇒「休憩5分」⇒「英語を25分間集中」のように、他の科目を間に挟んでも構いません。結局は苦手な科目もしっかりと勉強時間を取ってあげれば克服できます。
ただし、中学校三年生で、英語のbe動詞や三単現のSがわかっていなかったり、数学の一次方程式の計算が出来ていなかったりすれば、根本的な理解が出来ていないので、相当な時間と労力がかかってしまいます。少なくとも夏までには手を打たないと(ある程度克服された状態にしないと)、志望校の選択肢は限りなく少なくなってしまうでしょう。。
終わりに
多くの小学生や中学生は勉強が嫌いだったりつまらないという人が多いですが、その最大の原因は勉強しない(もしくは勉強時間が極端に短い)からです。勉強はどんな科目であってもある程度出来るようになるとそれなりに面白くなってきたり、やる気が出てきたりするものです。そこまで到達していないから、わからないしつまらないのです。集中力がないとかやる気が出ないという人は、まずこの「ポモドーロテクニック」を活用して25分間1つのことに集中してみましょう。そこから、「昨日は1ポモドーロやれたから、今日は2ポモドーロ頑張ってみよう」というようになってくればだんだん勉強が出来るようになっていき、知識も増えて、理解が深まっていきます。そうすることで自然と「勉強ってちょっと楽しいかも」と思えるようになってきます。この「ちょっと楽しい」という感情が芽生えてくることは勉強していく上で、とても重要なことです。勉強でもスポーツでも仕事でもあらゆることに関して言えることですが、楽しんでいる人が一番強いといえます。
ここで、中国の思想家である孔子の論語の言葉を紹介します。
「子曰く、これを知る者はこれを好む者に如かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如かず。」
(孔子は言った。あることを理解している人は知識があるけれど、そのことを好きな人にはかなわない。また、そのことを好きな人であってもそのことを楽しんでいる人には及ばないものである。)
まさに「好きこそものの上手なれ」です。勉強でもスポーツでも仕事でもそれを楽しみながらやっている人が一番ですね。
最後に、フォルテの中でも、集中力がないもしくは集中力をつけたいという生徒向けに「ポモドーロテクニック」を使った勉強のやり方を取り入れていこうと思っています。なので、その前に(実験的な意味合いもありますが)、実際にポモドーロテクニックを使って勉強してみたい方がいたら無料でやり方を教えます(タイマーさえあればだれでも出来ますが…)。日程としては、フォルテの授業がない金曜日で、なおかつ中学生のテストの対策のない日なので、5/31(金)か6/28(金)か7/5(金)あたりです。フォルテ生でもフォルテ生じゃなくても集中力をアップさせたいという方は是非。詳しくは045-334-8930またはforte.idogaya@gmail.comまで。ちなみにその際に、フォルテ生以外に子に対して強引な勧誘等は一切しませんのでご安心を。
最後にいつもの名言・格言を。
『どんな泥をなめてもいいし、はいつくばってでも結果出せばそれが一番かっこいい』
高木琢也(カリスマ美容師)


.jpg)

.jpg)
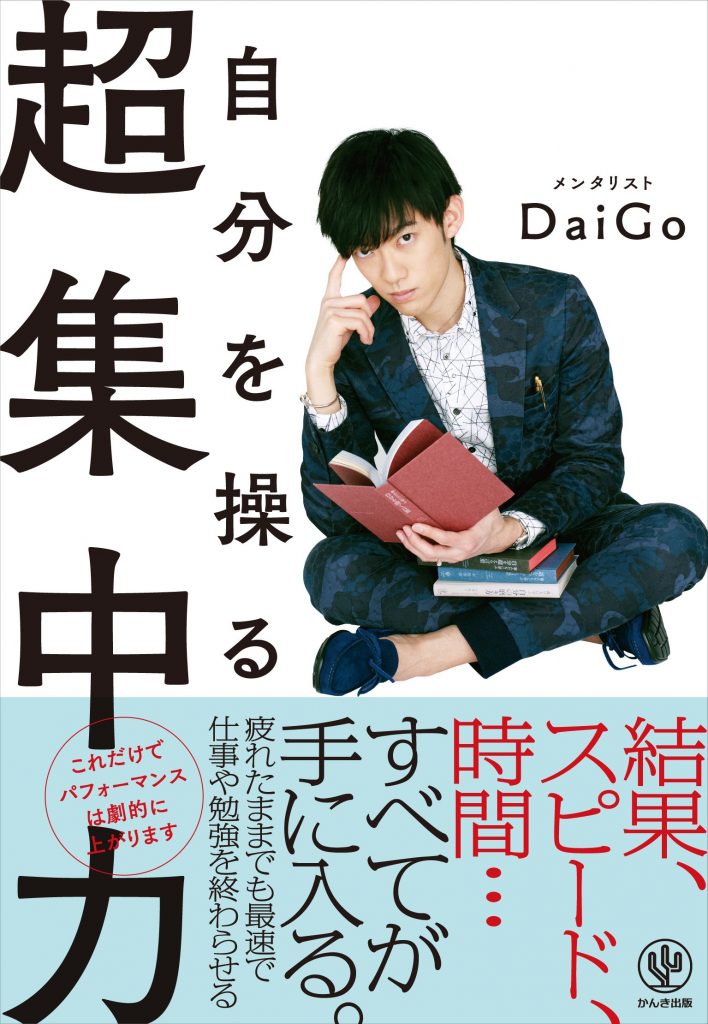

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)

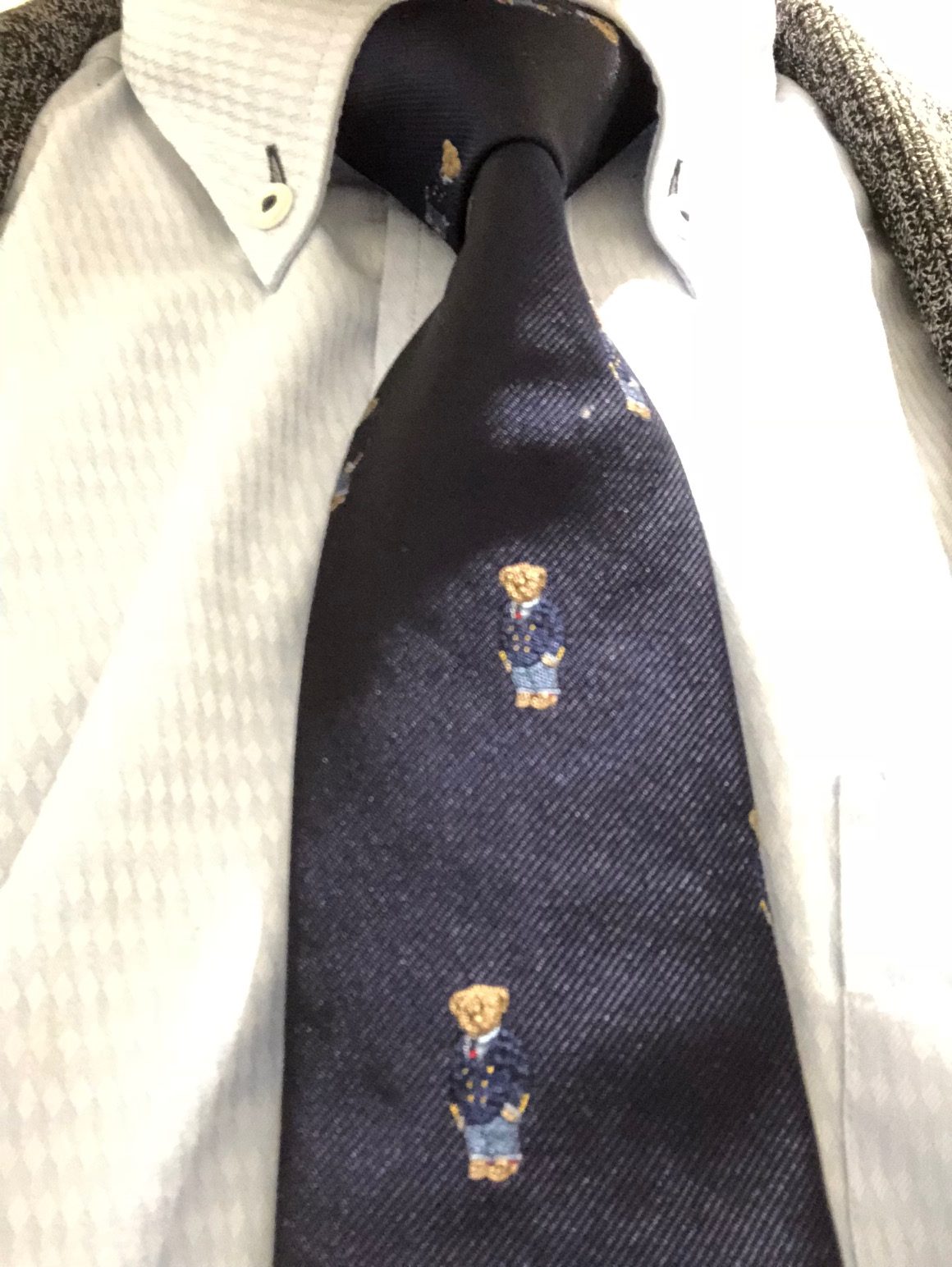
.jpg)
.jpg)

