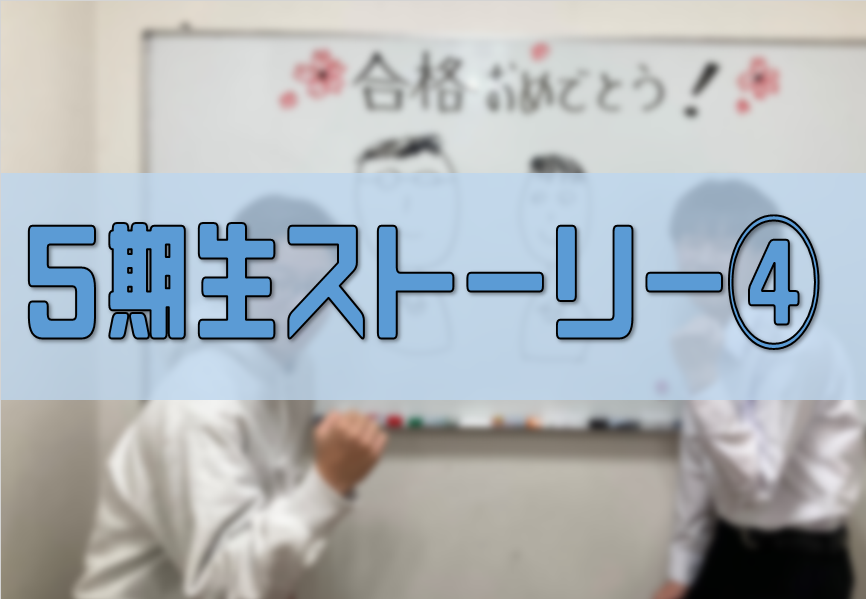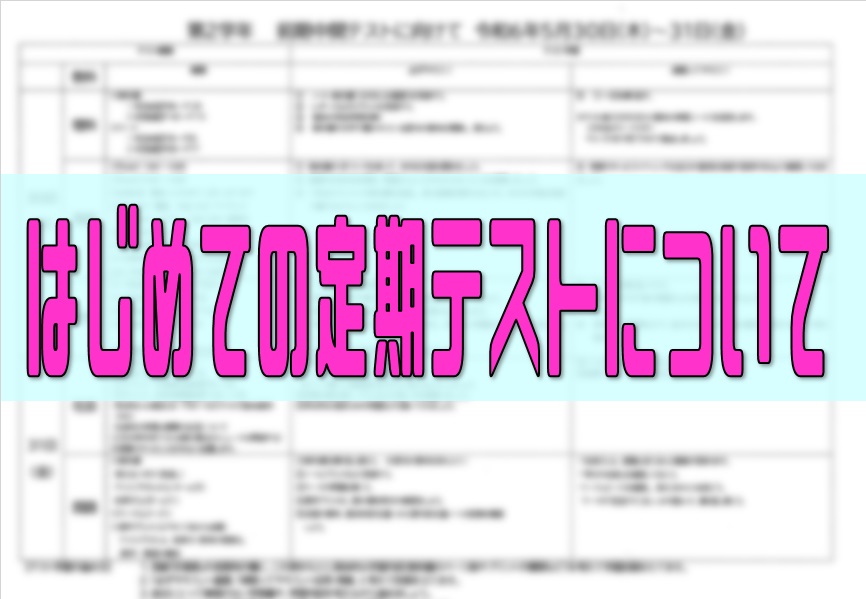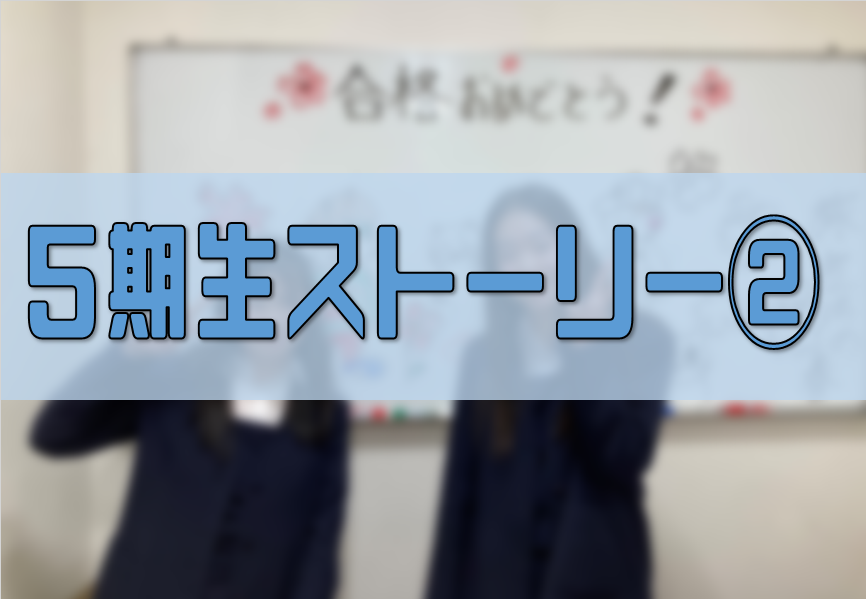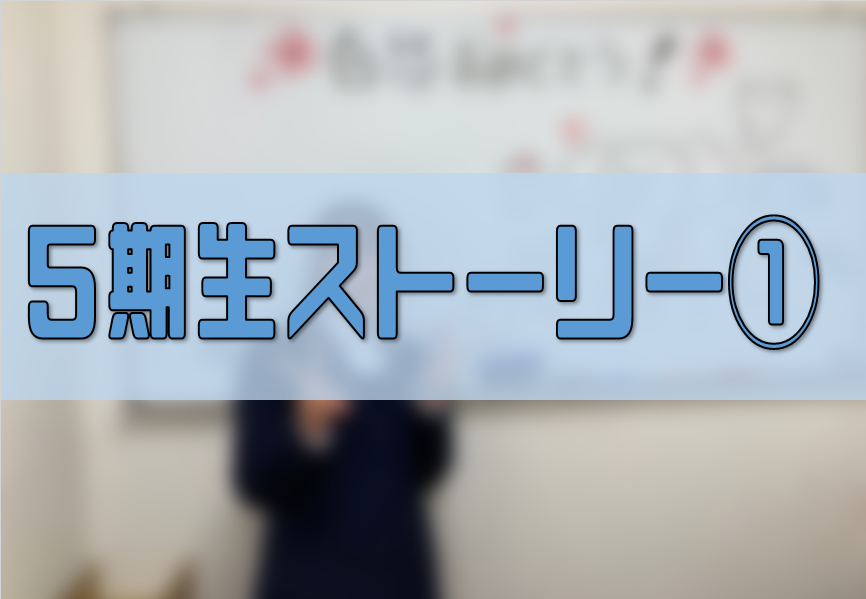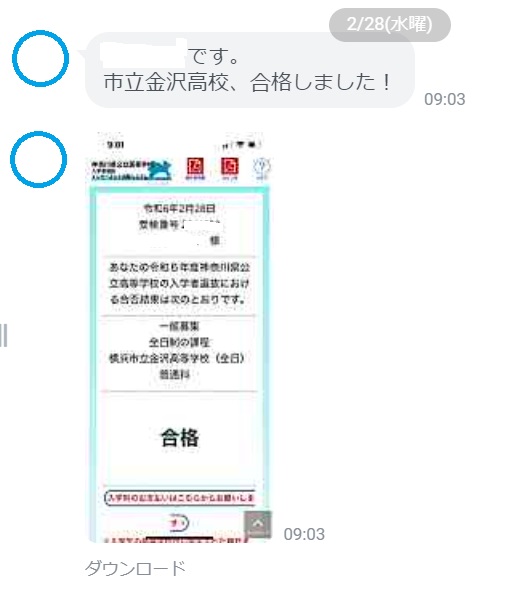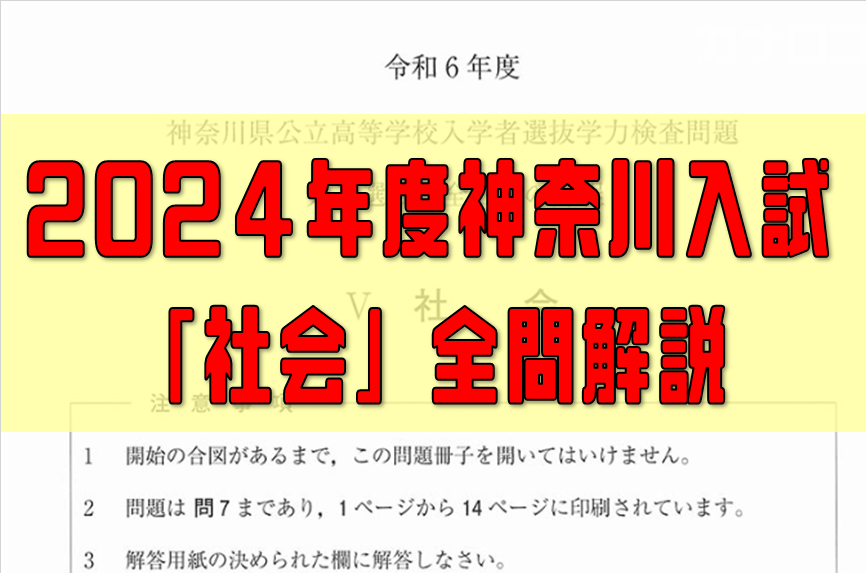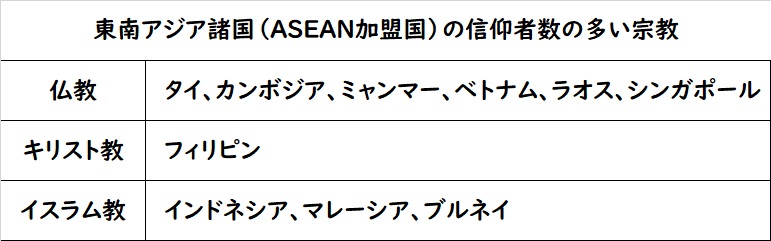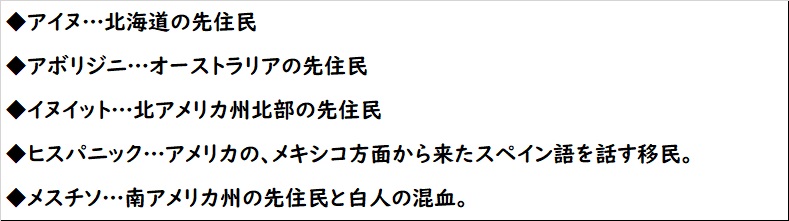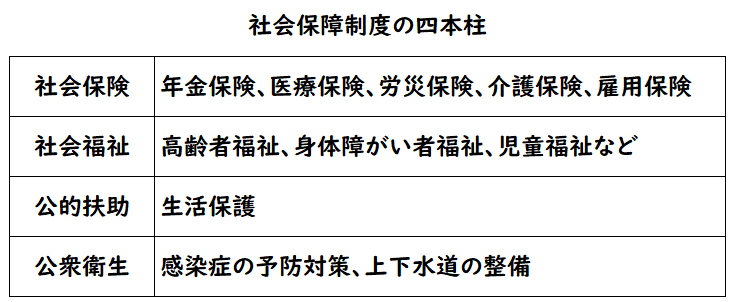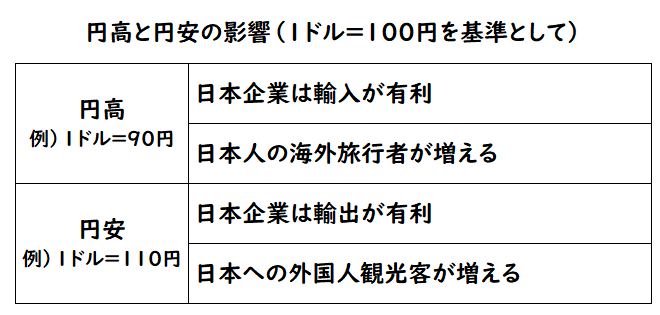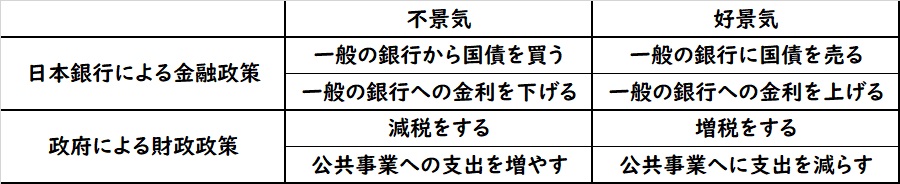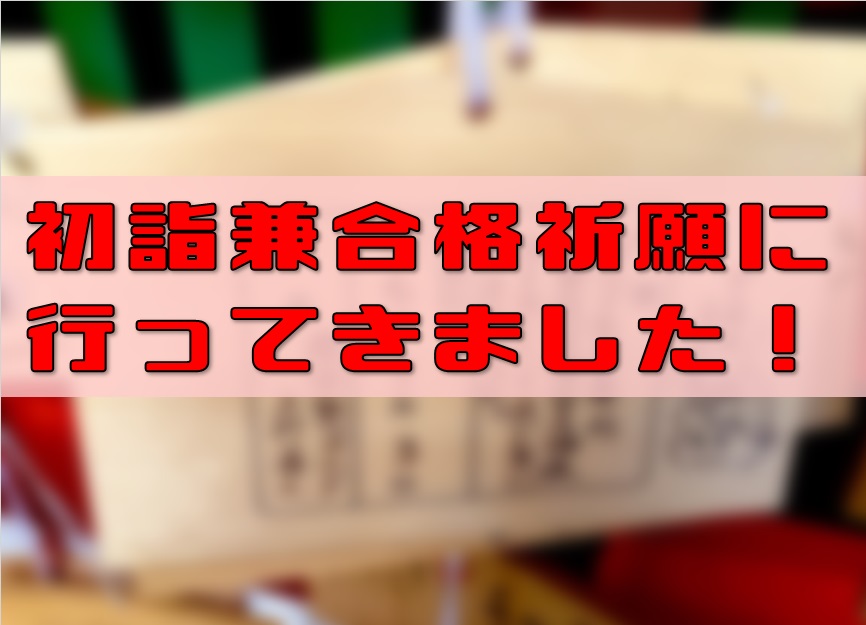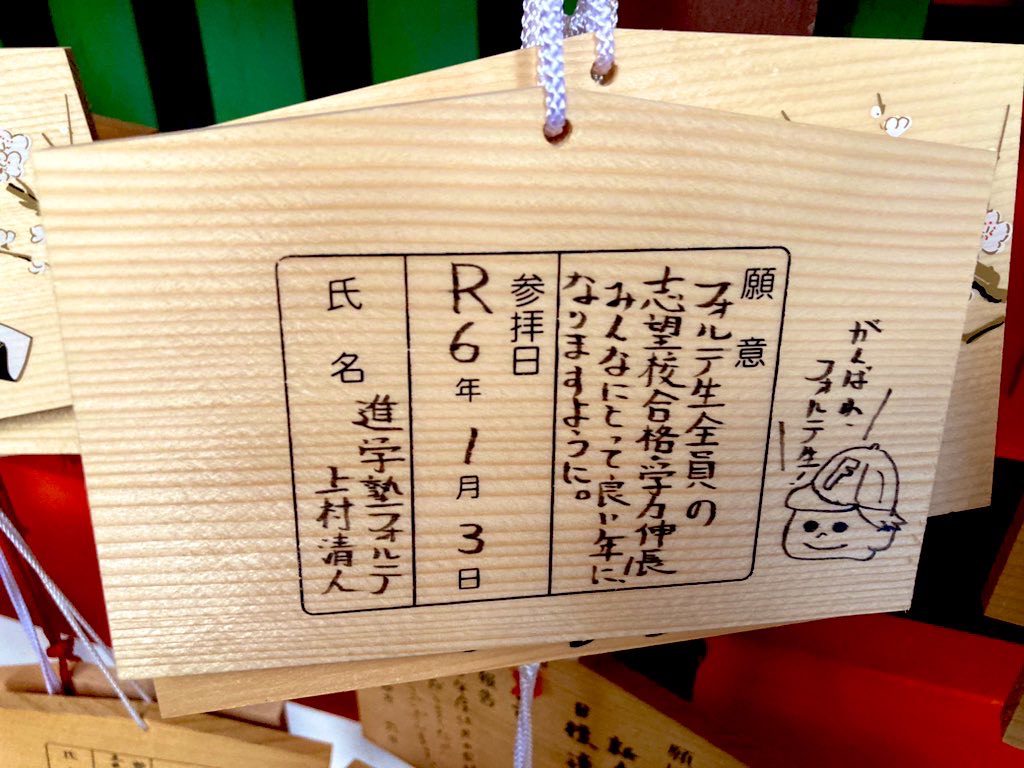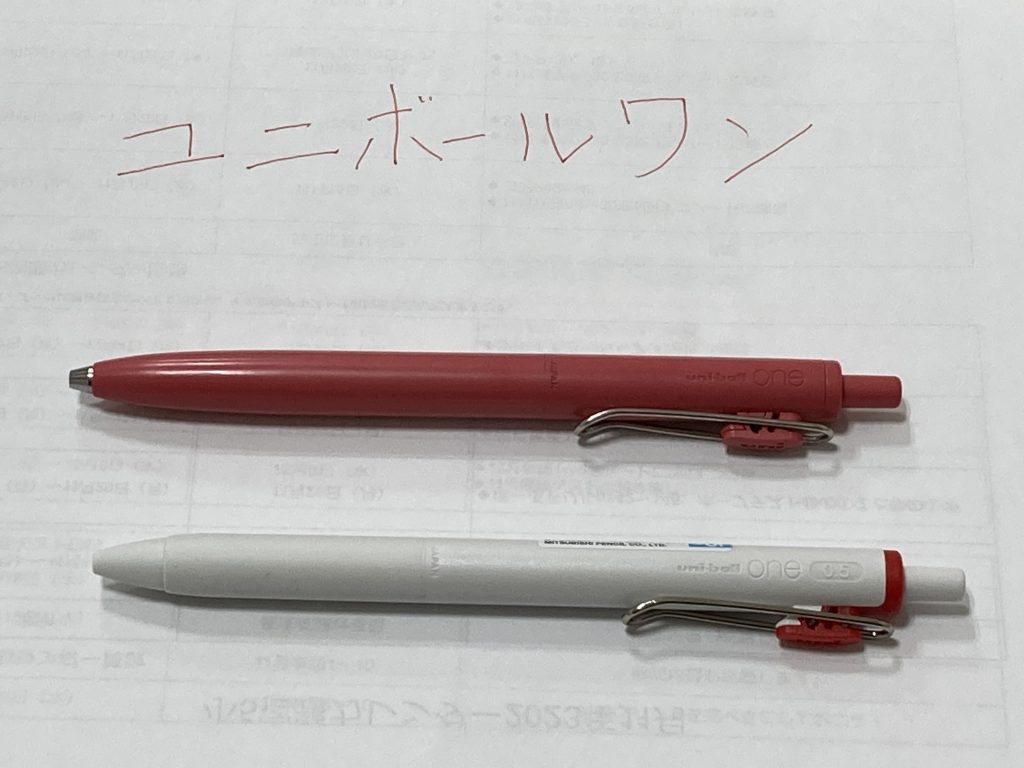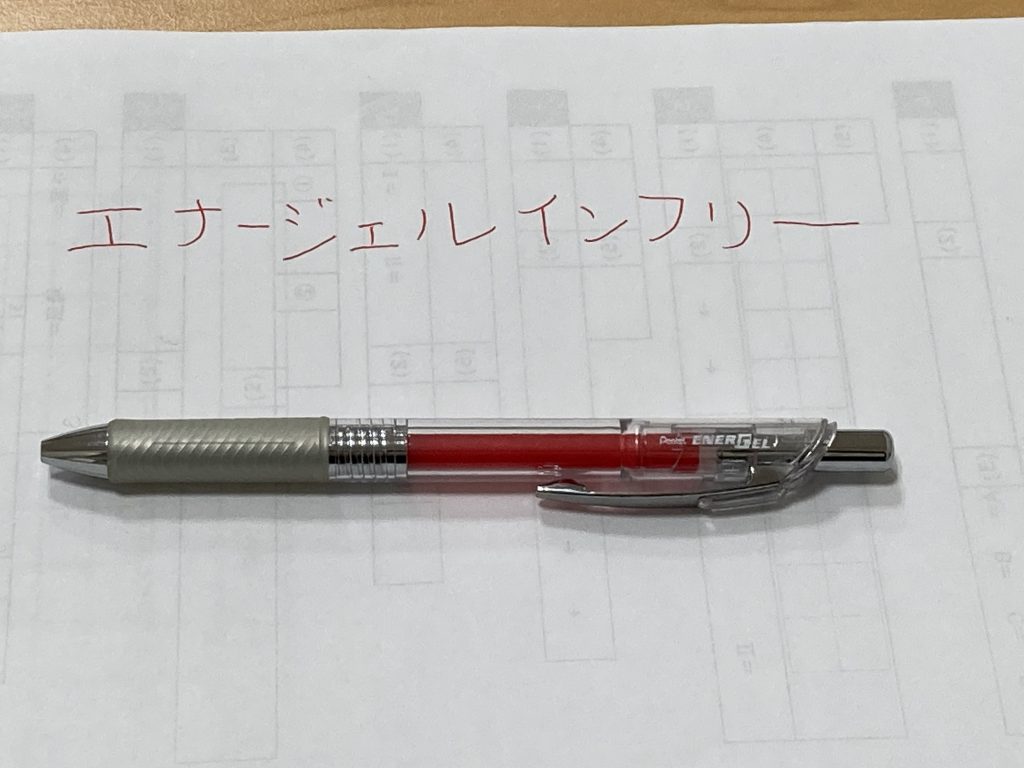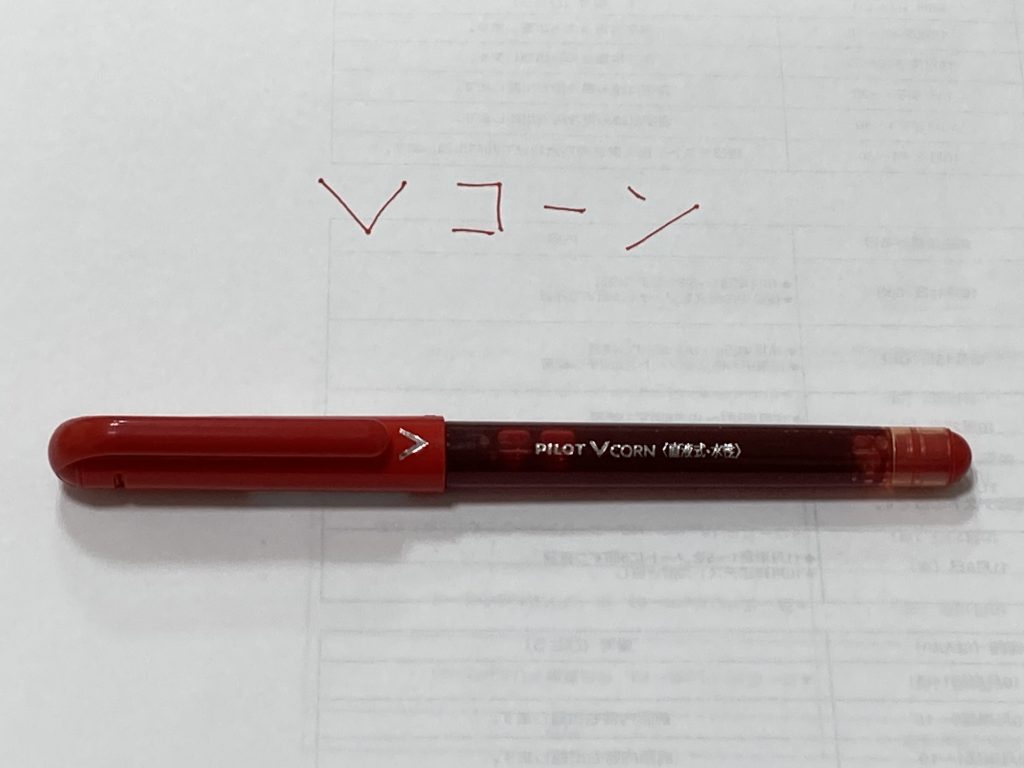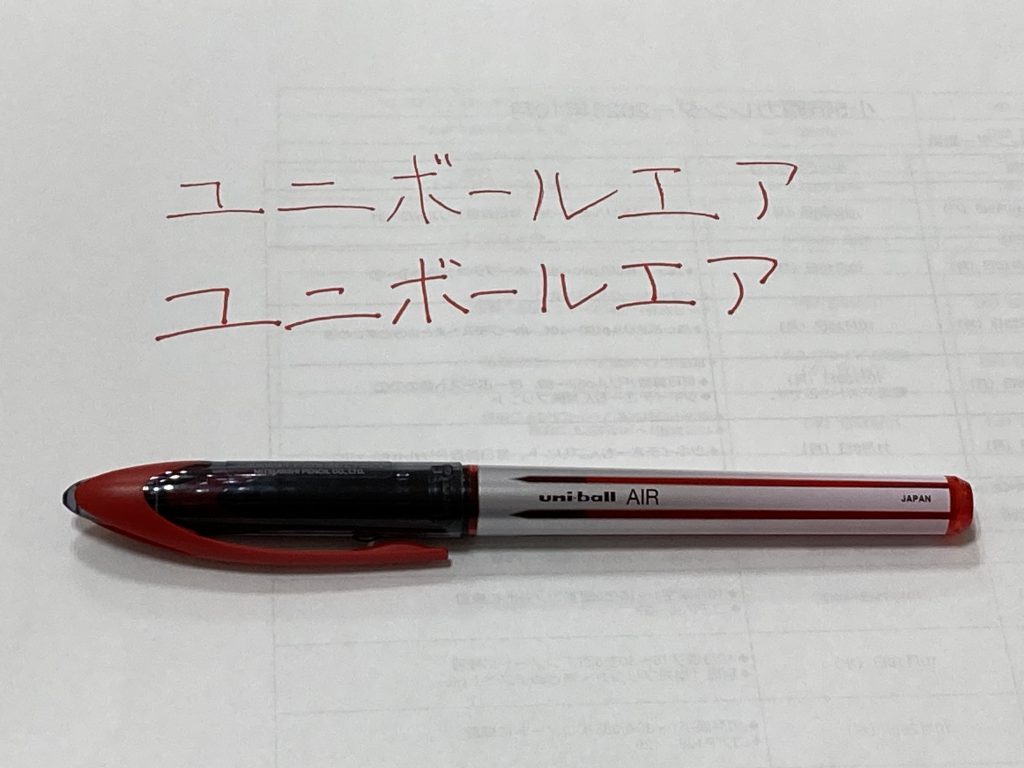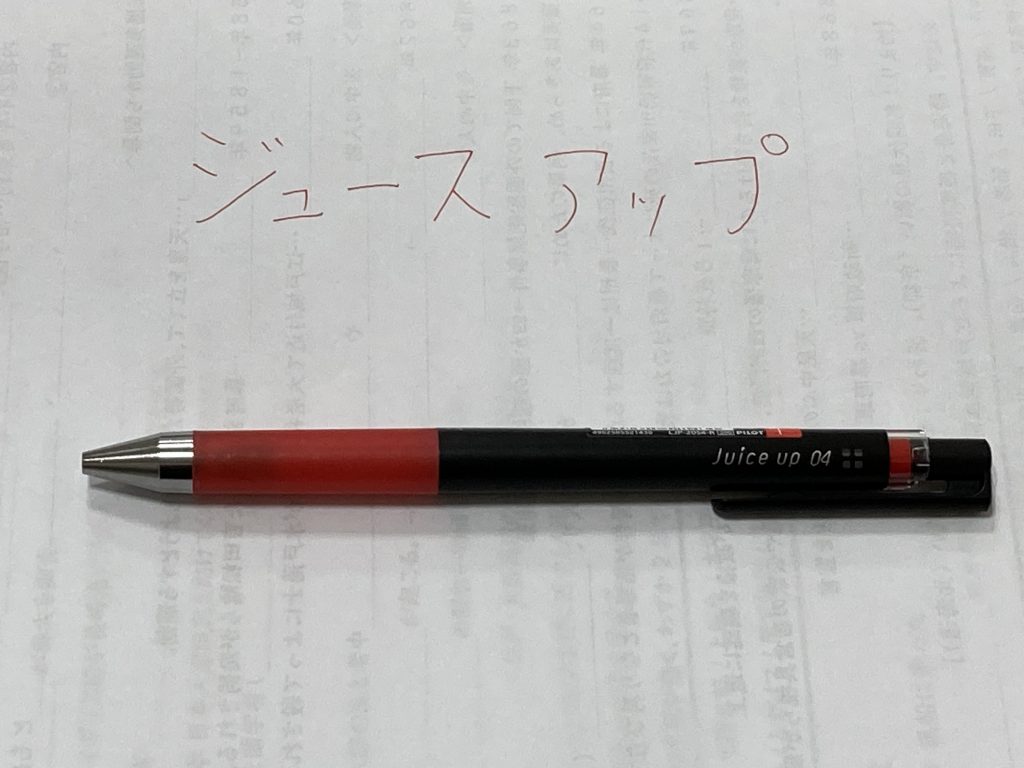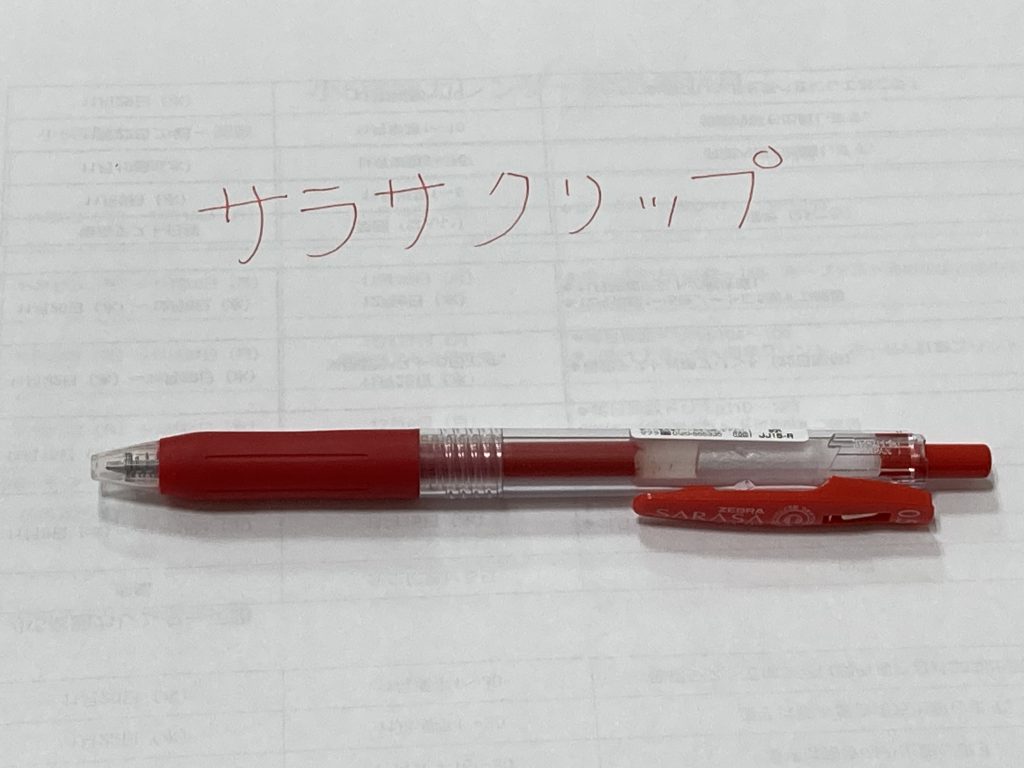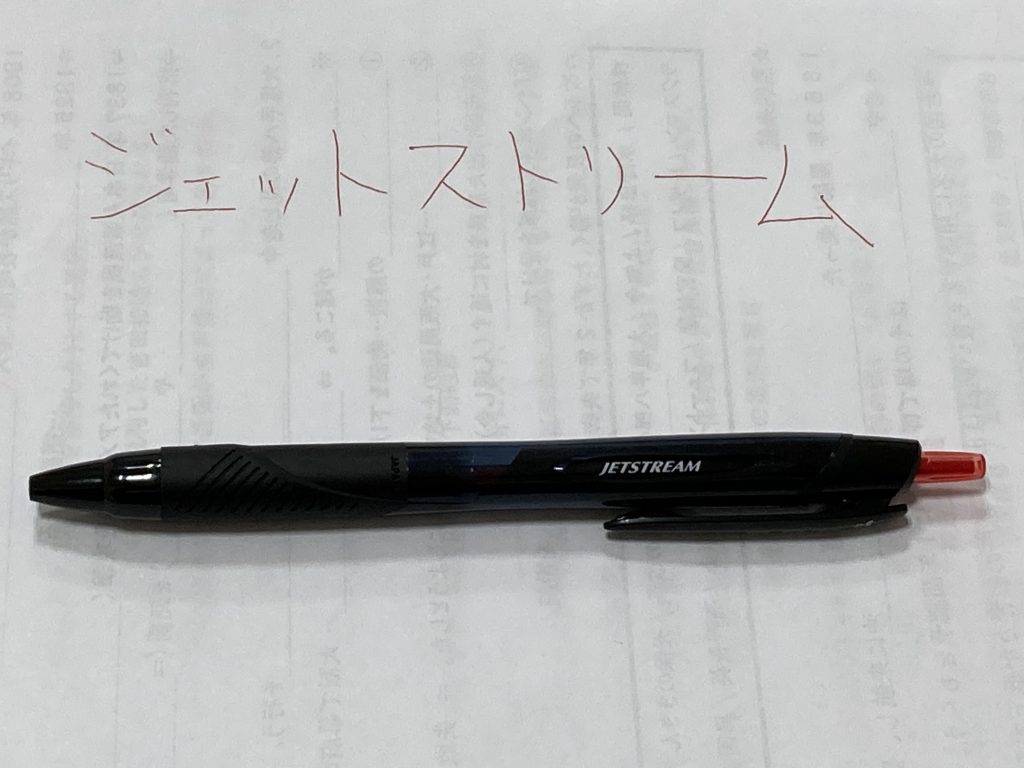こんにちは、フォルテの文系担当の上村です。
このシリーズでは、全小中学生にオススメの映画や小説などを紹介していきます。このシリーズで紹介するのは、私の考える「良い芸術作品」です。
ここでいう「良い芸術作品」とは、その作品に触れることで私たちが「何かしら成長できる」「何かを考えるきっかけを得られる」「何かしらを学べる」「モチベーションが高まる」作品を指しています。
優れた芸術作品(小説でも音楽でも絵画…etc)に触れることで私たちの人生は豊かになります。ここで紹介する良い芸術作品に触れることで少しでも子どもたちの人生が豊かになってくれればと思っています。
第十五弾となる今回は、映画『ルックバック』(2024年)です。

<参考記事>
第一弾:映画『ドリーム』(ココをクリック)
第二弾:映画『ズートピア』(ココをクリック)
第三弾:映画『シェフ~三ツ星フードトラック始めました~』(ココをクリック)
第四弾:映画『トイ・ストーリー4』(ココをクリック)
第五弾:映画『Us(アス)』(ココをクリック)
第六弾:映画『アルプススタンドのはしの方』(ココをクリック)
第七弾:映画『ミッション:8ミニッツ』(ココをクリック)
第八弾:映画『gifte/ギフテッド』(ココをクリック)
第九弾:映画『あの夏のルカ』(ココをクリック)
第十弾:映画『フリー・ガイ』(ココをクリック)
第十一弾:映画『ドラえもん のび太とアニマル惑星』(ココをクリック)
第十二弾:映画『ロスバンド』(ココをクリック)
第十三弾:映画『線は、僕を描く』(ココをクリック)
第十四弾:映画『さかなのこ』(ココをクリック)
目次
映画『ルックバック』とは?
映画『ルックバック』は、『チェンソーマン』『ファイアパンチ』などの作品で有名な漫画家・藤本タツキが2021年に発表した漫画『ルックバック』を映画化した作品です。漫画は発表直後から話題となり、「このマンガがすごい!2022」オトコ編1位に輝きました。
個人的には『チェンソーマン』は全く読んだことがなく、少年ジャンプ+というウェブサイト上で発表されたこの漫画版の『ルックバック』が初めて読んだ藤本タツキ作品でした。
原作漫画をかなり忠実に映画化された今作は、上映時間58分と中編作品ながらもその中にものすごく濃密な物語や描写が練り込まれています。これは、最高の青春映画であり、最高の仕事映画となっていて、学生から社会人まで老若男女に刺さる傑作だと思います。
映画『ルックバック』のあらすじ
学年新聞で4コマ漫画を連載している小学4年生の藤野。クラスメートから絶賛され、自分の画力に絶対の自信を持つ藤野だったが、ある日の学年新聞に初めて掲載された不登校の同級生・京本の4コマ漫画を目にし、その画力の高さに驚愕する。以来、脇目も振らず、ひたすら漫画を描き続けた藤野だったが、一向に縮まらない京本との画力差に打ちひしがれ、漫画を描くことを諦めてしまう。
しかし、小学校卒業の日、教師に頼まれて京本に卒業証書を届けに行った藤野は、そこで初めて対面した京本から「ずっとファンだった」と告げられる。
漫画を描くことを諦めるきっかけとなった京本と、今度は一緒に漫画を描き始めた藤野。二人の少女をつないだのは、漫画へのひたむきな思いだった。しかしある日、すべてを打ち砕く事件が起きる…。
映画『ルックバック』の見どころ
努力の描写
藤野は、自身が4コマ漫画を連載していた学年新聞で初めて京本の絵を見て衝撃を受けます。写実的に描かれたその絵は、自分よりも圧倒的に上手いものでした。それまでは身の回りの人々から口々に「絵が上手い」とチヤホヤされて、自分の画力に自信があった藤野としては到底受け入れられない事実です。学校からの帰り道、
「4年生で自分より絵ウマいやつがいるなんて、絶っっ対に許せない!」
と思い、その「怒り」が藤野の闘争心に火を付けます。
そこから、藤野は本格的に絵が上手くなるために、自分で色々と調べ、教則本やスケッチブックを買い、狂ったように絵を描きまくります。家にいるときは部屋にこもって描きまくり、学校でも友人との会話そっちのけで描きまくります。
机には次第に教則本が増えていき、描き終えたスケッチブックもどんどん積み重なっていきます。また外の風景で季節が移り変わり、そこから藤野は約2年間ひたすら絵を描き続けたことがわかります。そんな藤野は、家族や周りの友人から「いつまでマンガ描いてるの?」「中学で絵を描いていたら、オタクだと思われちゃうよ?」などと言われてしまいます。それでも藤野は描き続けます。すべてはあの時の「怒り」から始まり、「京本に負けたくない」という一心でした。
こういった主人公の努力の描写が個人的に大好きです。冒険やバトルがテーマの作品における修行のシーンも同じで、こういった描写があることで、そのあとに主人公が良い成果や結果を手に入れたときに、見ている私たちが感じる感情の波は確実に大きくなります。
また藤野のように「怒り」や「悔しさ」が何かを頑張る原動力になるというのも共感できます。私自身も、今の仕事を頑張るモチベーションの1つに前職(大手塾勤務)時代に抱えていた怒りや悔しい思いを晴らしたいというのがあります。特にフォルテ立ち上げ当時はその思いは強かったです。
また、私の尊敬するお笑い芸人・山里亮太(南海キャンディーズ)さんも著書の中やインタビューなどで「妬み嫉みはガソリンです」と述べています。
尊敬する相手に認められる喜び
6年生の途中、自分自身は着実に成長しているものの、一向に京本との画力の差が埋まらないことで、すっかり漫画への熱が冷めてしまい、絵を描くことをやめてしまった藤野。そこからは家族と一緒にテレビを見たり、姉の通う空手教室に通ったり、友達と遊んだりと、絵を描いていたときにはできなかったことをやって充実した小学校生活を送ります。
そして、卒業式の日。職員室に呼ばれた藤野は担任の先生から、京本の家に卒業証書を届けるように頼まれます。嫌々ながらも教えてもらった住所をたよりに京本の家に着き、インターホンを押します。しかし中からの反応はありません。ただし、玄関のドアが開いていたので、中に入って玄関口に卒業証書を置いて帰ろうとした瞬間、奥の部屋から何やら物音がします。「なんだいるんじゃん」と思い、靴を脱いで家に上がり、廊下を歩いて進み、物音がした部屋の前まで来ます。すると、そこには何十冊ものスケッチブックの山がありました。目の前の部屋の中にいるのは京本に違いありません。つまり、京本の小学生離れした圧倒的な画力は決して才能ではなく、途方もない努力の積み重ねの結果だったのです。
そこでスケッチブックの山の上に、白紙の4コマ漫画用の紙を見つけ、その場でささっと漫画を描くことにする藤野。完成した漫画を手に持っていると、それがふと手からこぼれ落ちて、目の前のドアと床の隙間から部屋の中に入ってしまいました。思ってもいない結果に、慌てて藤野はその場を離れ、京本の家を出ます。すると、すぐに家のドアが開き、はんてんを着た女の子が飛び出してきます。その女の子は開口一番、「藤野先生!」と発します。不登校でずっと部屋に閉じこもっていた京本は、実は学年新聞に連載していた藤野の漫画の大ファンだったのです。そんな京本からすると、急にドアの隙間から4コマ漫画が入ってきて、しかもそれが自分が憧れる「漫画家」である藤野の作風だったので、いてもたってもいられずに部屋を飛び出してきたのでした。自分よりもはるかに画力が上で尊敬していた京本から自分の漫画が認められて、さらに自分のことを「漫画の天才」だと言ってくれたことで、藤野は漫画への熱を取り戻します。
そこからの帰り道。最初はうつむき加減に歩いていた藤野でしたのが、いつの間にか背筋が伸び視線は前を向き、ついには足取りがスキップになり、踊るようにしてあぜ道を進むのでした。それは尊敬していた京本に自分の漫画が認められていたこと知り、その喜びがだんだんとこみ上げてきて、ついには爆発した藤野を描写した、今作でも最高のシーンの1つです。
青春映画として『ルックバック』
中学生になって漫画の共作を始めた藤野と京本。ストーリーやメインのビジュアルを藤野が担当し、京本は背景を担当します。そこから1年を要して完成させた初作品『メタルパレード』を、二人は藤野キョウ名義で出版社に持ち込みます。それは編集者からも絶賛され、『メタルパレード』は週刊漫画誌の漫画賞で準入選(賞金100万円!)を果たします。
その賞金の一部を銀行口座から下ろしてきた藤野は京本を誘って、二人で街に繰り出します。そこで、スイーツを食べたり、映画を見たり、本屋にいったり、二人は1日中遊びます。それまでずっと不登校で家に引きこもっていた京本にとっては、こういった「外の世界」で中学生らしく遊んだ経験は全くありませんでした。しかし、藤野に引っ張られることで自分の知らなかった世界を知れたこと、知らなかった楽しさに出会えたのです。そこで京本は自分に部屋から出るきっかけをくれた藤野に感謝します。
そこから二人は高校卒業までに7本の読み切り作品を発表します。この読み切り作品を作る過程がまた素敵です。二人が実際に海にいったり、公園でセミを観察したり、二人の思い出がそのまま作品の着想元になっているのです。つまり、二人が中学から高校にかけて共作した読み切り作品は二人にとって青春そのものなのです。この瑞々しい二人の青春パートを見ているだけでも涙が出てきます。
原作に忠実な映画化
今作は、かなり原作漫画に忠実な形で作られています。ただ、それだけでなく原作では表現しきれなかった部分を映像化することや新たなシーンを加えることで、原作漫画の世界観をさらに解像度高く味わうことができるようになっています。
エモーションを高める音楽
今作は、音楽を haruka nakamura が担当しており、印象的なピアノ音楽が各シーンで流れ、原作で感じたエモーションを何倍にも高めることに成功しています。
映画『ルックバック』後半ネタバレ&感想
ネタバレ有の後半の展開
二人は高校3年生のときに出版社から、高校卒業後に週刊漫画誌で連載を持たないかと誘われます。喫茶店でその話を聞き、大喜びの藤野の一方で、どこか表情の冴えない京本。その帰り道、京本は高校卒業後に美術大学に進学したいという思いを藤野に打ち明けます。最初は反対していた藤野ですが、京本の「もっと絵が上手くなりたい」というまっすぐな気持ちに何も言えなくなってしまいました。ここで二人は別々の道を歩むことになります。
京本とのコンビを解消した藤野でしたが、藤野キョウというペンネームは変えずに週刊漫画誌で連載を持ちます。初めての連載作品『シャークキック』は、最初こそ人気が低迷していましたが、巻を重ねるごとにだんだんと人気が出てきて、アニメ化も決定しました。しかし、藤野は問題を抱えていました。それはアシスタントが自分の思う通りに描いてくれないことでした。漫画家にとって、背景などを描くアシスタントは不可欠な存在です。編集部の人にも色々と相談して何とか連載を続けている状況でした。
そんなとき、偶然つけていたテレビからあるニュースが流れてきます。それは「山形県の美術大学に不審者が侵入して学生らを切りつけた」というものでした。そこは紛れもなく京本が進学した大学でした。胸騒ぎがした藤野は京本に電話を掛けますが、京本は電話に出ません。そこに母親からの着信。そこで母親から告げられた話は藤野が一番聞きたくない事実でした。テレビニュースで流れていた事件で亡くなった被害者の一人が京本だったのです。
※この事件の描写自体は2019年の京都アニメーション放火事件を意識したものだと思います。
ここで藤野は京本とのある会話を思い出します。それはとある雪の日。二人は将来について語り合います。
「もしウチらが漫画を連載できたらさ、すっごい超作画でやりたいよね」
と言う藤野に対して、
「私は描くのが遅いからなぁ。もっと早く描けたらいいんだけど…。」
と京本は不安を口にします。それに対して藤野は、
「んなの楽勝でしょ。画力が上がればスピードも速くなるんだよ!」
と伝えます。そこで京本は、
「じゃあ、もっと絵上手くなるね!藤野ちゃんみたいに。」
と言います。
つまり、京本が美術大学に進学したい理由として挙げていた「もっと絵が上手くなりたい」というのは、「藤野の描きたい漫画のアシスタントになれるような実力をつけたい」ということだったのです。
連載中の「シャークキック」も休載し、藤野は通夜のために京本の家を訪れます。久々に京本の部屋の前に来ると、部屋の前には以前と変わらずスケッチブックの山があり、その一番上には「シャークキック」が連載している週刊漫画誌がありました。そっと手に取り、何気なくペラペラとめくっていくと、その途中でしおりのようにある細長い紙が挟まっていました。よくよく見ると、それは小学校の卒業式の日に藤野が描いた4コマ漫画でした。そこで藤野は、元はといえばこの4コマがきっかけで京本は部屋から出るようになった。この4コマ漫画さえなければ、京本は部屋から出ることもなかったし、理不尽に殺されることもなかったと思い、自分がこの4コマ漫画を描かなかった世界線を想像します。
その世界線では、美術大学で不審者に襲われる寸前の京本を、偶然通りかかった空手少女・藤野が助け出します。そこで京本は自分を助けてくれたのが、以前自分が学年新聞で大ファンだった「藤野先生」だと知ります。ちょうどそのとき漫画を再び描き始めたという「藤野先生」と京本は、この偶然の出会いによって、そこから二人は漫画家とアシスタントの関係になるように描かれます。
そんな想像をする中、京本の部屋の中から、ドアと床の隙間からある細長い紙が出てきます。それは京本が描いた4コマ漫画でした。それに導かれるように藤野は京本の部屋に入ります。そこには「シャークキック」のポスターが貼られ、単行本も同じ巻が何冊も並び、机の上には読者アンケート用のはがきもありました。そこで藤野は、京本は美術大学進学後も自分の漫画の大ファンであったことに気づきます。しかも、まだ人気がなかった連載当初の単行本が何冊も並んでいたのは、京本がわざわざ何冊も買って藤野キョウを支えていたということでしょう。
そこで二人の過去の会話が思い出されます。
「漫画ってさあ、私描くのまったく好きじゃないんだよね。楽しくないし、メンドくさいだけだし、超地味だし。一日中ず~っと描いてても全然完成しないんだよ?読むだけにしといたほうがいいよね、描くもんじゃないよ。」
そう言う藤野に京本が聞き返します。
「じゃあ、藤野ちゃんはなんで描いてるの?」
それに対して、セリフでの答えはないのですが、藤野の頭に浮かぶのは、自分の漫画を読んで誰よりも興奮したり、喜んだりしてくれる京本の姿なのでした。
そんなことを思い出した藤野は、再び漫画を描き始めます。京本が大好きだった自分の漫画を。
仕事映画として『ルックバック』
この最後のシーンは、原作漫画の通りなのですが、映像で改めて見ると個人的にかなりグッと来ました。「なぜ藤野は漫画を描くのか?」「それは一番のファンである京本の喜ぶ顔が見たいから。」という結論です。これ以外にも小学生のころに藤野がなぜ学年新聞に漫画を描き続けていたのかというと、それを読んで楽しんでくれる同級生たちのためだったのでしょう。
この映画を見て、私はハッとしました。これは漫画家に限らず多くの仕事に従事する人に共通するモチベーションや原動力の本質なのではないかと思ったわけです。つまり、多くの人々がキツいことや大変なことがあるの中でも自分の仕事を頑張る理由って「ファン(=客)の喜ぶ顔が見たいから」じゃないのかな、と。
ということで、私はこの映画を見ることで仕事へのモチベーションが大いに上がりました。
タイトルの『ルックバック』の3つの意味
タイトルの『ルックバック(=look back)』には、3つ意味合いがあると思います。
まず1つ目はストレートに訳すと「(過去を)振り返る」という意味ですので、理不尽な出来事が起きたことで、「もしもあの時…」のようにパラレルワールド的に過去を振り返るという物語の後半の展開を表しています。原作漫画もそうですが、「現実の救いようのない出来事を創造力・創作で乗り越えることができるのか」という展開になります。これは、同じようなテーマの映画のポスターがいくつも主人公の部屋に貼ってあることからもわかります。また、このテーマについては、原作者の藤本タツキさん自身が美術大学在籍時に東日本大震災を経験したことが大きいそうです。
次に2つ目は「背中を見る」という意味です。原作でも映画でも「背中」や「後ろ姿」がかなり強調されています。もちろんメインとしては、藤野と京本の二人の関係です。漫画のストーリーを考える才能のある藤野の背中を見る京本、圧倒的な画力を持つ京本の背中を見る藤野。まさにお互いをリスペクトし合い、切磋琢磨し合う関係の絶妙な二人を象徴する言葉です。
最後に3つ目は「背景を見る」ということです。物語内では京本は漫画の背景を担当しています。主人公の藤野は、原作者である藤本タツキさんを投影したキャラクターだと思います。そこで、自分(作者)を支える存在が背景を描くアシスタントです。なので、恐らく背景担当のアシスタントやスタッフへの感謝やそういった方々の仕事にスポットライトを当てたかったのではないかと思います。
また、原作漫画からイギリスのロックバンドの oasis の名曲「Don’t look back in anger.」の文字を何気なく入れ込むなどの遊び心もあります。この曲自体もこの作品のテーマに大きく影響を与えているのでしょう。
ということで、映画『ルックバック』を是非ご覧ください!
今回は以上です。ではまた!

進学塾フォルテ|俺たちが井土ヶ谷・蒔田・弘明寺地域を熱くする!|各学年12名までの少人数制対話型集団授業